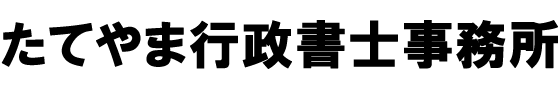飲食店を開業するには、具体的にどんな準備や手続が必要なのでしょうか?
初めて飲食業界に算入される方はもちろん、飲食店で長く働いていても、法律上の細かな決まりまでは普段は意識しないので、いざ開業するとなると、迷われる部分もあるかと思います。
そこで、
●飲食店を始めるにはどんな手続きが必要なのか?
●飲食店を始めるのに資格や実務経験は必要なのか?
飲食店を開業するために必要な手続についてお話しています。

ポイント① 保健所の「営業許可」が必要
飲食店は、人の口に直接入る飲食物を扱う仕事です。
「白衣を着るのは医者と料理人のみ。それは命に関わる仕事だから」(と先輩が言ってた)
そんなふうに言われるほど、人の健康や生命に直接かかわる仕事ですので、営業するにあたっては、食中毒などの健康被害が起きないように適切な衛生管理が必要です。
そうした理由から、飲食店を始めるには、事前にお店の所在地を管轄する保健所から許可を得なければならないことになっています。
(『飲食店営業許可』)

肉や魚、野菜を扱う料理店はもちろん、スナック菓子や乾き物しか扱わないバーのようなお店も、人の口に入る飲食物を扱う以上は、例外なく営業許可が必要です。
飲食店の営業許可を取得するには、
(1)衛生管理の責任者を一人置き、
(2)法律上決められた基準を満たす構造・設備を備えた店舗をつくり、
(3)保健所の検査に合格する
ことが必要です。
申請から検査まで一週間程度、検査合格から許可書ができるまで約一週間程度かかります。
(飲食店の営業許可について詳しくはこちら)
ポイント② 「食品衛生責任者」が必要!
飲食店には、店舗ごとに、衛生管理の責任者となる人が必要です。(食品衛生責任者)
この食品衛生責任者になることが出来るのは、一定の衛生管理に関する知識を持った人に限られます。
具体的には、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する人ですが、そうした資格を持っていなくても、食品衛生責任者となるための「養成講習」を受講すれば責任者となることが出来ます。

ですので必ずしも調理師や栄養士の資格を持つ人を雇い入れる必要はなく、店長としてお店を任せる人に講習を受講してもらうか、自分で受講すれば大丈夫です。
なお、「養成講習」は各都道府県で随時行われていますのでいつでも受講が可能です。
ただし常に予約でいっぱいなので、早めに受講するようにしましょう。
(詳しくはこちら)
ちなみに、経営者にも食品衛生責任者にもy、実務経験等は求められていません。
手続上の要件としては、養成講習を受講した衛生責任者がいれば、お店を始めることが出来ます。
ポイント③ 法律上の基準を満たす設備が必要!
飲食店の営業許可を取得するためには、衛生的に営業をしていくのに十分な構造と設備が必要です。
具体的にどんな構造・設備があればよいのかは法律で細かく定められています。
その基準を満たしたお店をつくり、保健所の検査をクリアしなければなりません。
(詳しい基準についてはこちら)
許可を受けることなく営業を始めてしまうと無許可営業として処罰の対象となってしまいます。必ず許可を受けて営業するようにましょう。

内装工事前に確認を!
このように、お店の物件を契約したうえで必要な内装工事、設備工事をし、必要な機器等を搬入して初めて、許可に必要な検査を受けることが出来ることになります。
ということは、もしも検査時に、設備が基準に適合していないとして変更や修正を求められたりすると、追加の費用や時間がかかってしまう可能性があります。
スケルトン物件(内装がすべて撤去されている状態の店舗)で一から工事を入れるのであれば、設計段階で保健所に一度基準を満たしているか確認しましょう。
居抜き店舗(もともと飲食店舗で、内装や設備が残っているもの)や内装リース付きの店舗であれば、ある程度基準を満たしていることが期待できますが、必要な設備が撤去されてしまっていたり、老朽化などで交換が必要な場合もあります。あらかじめ確認するようにしましょう。
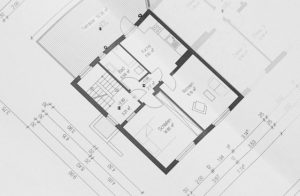
ポイント④ 深夜にお酒を提供するには警察に届出を!
バーや、スナック、深夜営業の居酒屋など、深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)にお酒を提供して営業する場合は、営業開始の10日前までに警察に届出が必要です。
(深夜における酒類提供飲食店営業 営業開始届)
このような深夜酒類提供飲食店は、いわゆる風営法の規制を受けることになります。

通常の飲食店(食品衛生法)の基準とは別に、風営法上の構造・設備基準が適用されますので、内装工事の際はこちらにも注意しておく必要があります。
お店の検査こそありませんが、届出時には詳細な店舗の内装図面、求積図面など添付する必要があります。
また、営業開始後は立ち入り検査に応じる義務がありますので、あとあと指摘を受けたりすることがないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
営業できない地域がある
深夜酒類提供店は、都市計画法上の住居集合地域では営業することが出来ません。
バーやスナックの営業を検討している場合は、物件を選ぶ際、必ず「用途地域」を確認するようにしてください。

ちなみに、深夜0時までの営業であれば、保健所の飲食店営業許可のみでお酒も提供することが出来ます。
この点、キャバクラなどの社交飲食店は1時まで営業時間の延長が許される地域がありますが、深夜における酒類提供飲食店にはそのような規定はありません。
「1時までなら届出をしなくてもよい」とか、「繁華街だから届出はしなくてよい」ということはありませんのでご注意ください。
なお、24時間営業のファミレスやラーメン店、牛丼店など、主に食事を提供するお店は対象外です(届出不要)。
(深夜営業の届出について詳しくはこちら)
ポイント⑤ 社交飲食店は風営許可も必要!
スナックやキャバクラなど、「接待」を伴う飲食店を営業する場合は、「飲食店営業許可」のほか、警察署を通じて、都道府県公安委員会より「風俗営業(社交飲食店)」の許可を取得する必要があります。
テーブルに(主に)異性のキャストがつくお店や、料亭のように各客室で踊りや歌を聴かせるようなお店が代表的ですが、ガールズバーのような業態でも、実質的に「接待」にあたる営業をしていれば風営許可が必要な場合があります。

たとえば、特定のお客(グループ)に対して継続して接客をしたり、一緒にダーツやカラオケをしたり、身体に接触してダンスをしたりする場合は、「接待」に該当する可能性が高いです。
許可を取得しないままで「接待」を伴う営業をしていると、無許可営業として摘発の対象となってしまいますので注意が必要です。
なお、風俗営業の許可を得て営業する場合は、一部の繁華街を除き、深夜0時以降に営業をすることはできません。
一定の施設が近くにあると営業できない
社交飲食店も、深夜酒類提供飲食店と同じく住居地域では営業が出来ません。
また、学校や児童養護施設、病院等(保全対象施設)が一定の距離内にあると営業ができないことになっているため、社交飲食店の営業を考えている場合は物件を選ぶ際によく確認するようにされてください。

近くにパチンコ店やマージャン店、社交飲食店があっても、新たにこうした施設が出来ていると許可は出ません。居抜きや名義変更などで、前の店舗が社交飲食店だった場合も同様です。
内装や設備にも制限がある
社交飲食店も、風営法により内装や設備に制限があります。
客室内に衝立などの見通しを妨げる設備があったり、調光設備、施錠設備があったりすると許可がおりません。こうした風営法上の基準を満たしたうえで、検査を受けてクリアする必要があります。

ただでさえ、風営許可は、申請から許可が出るまでに時間がかかります。
(審査期間が55日以内)
検査で不備があり再検査となってしまうと、余計に時間・費用がかかってしまう可能性がありので、事前に確認しながら進めていく必要があります。
(風俗営業(社交飲食店)許可について詳しくはこちら)
ポイント⑥ 消防にも「使用開始」の届出を
飲食店や社交飲食店は、不特定多数の人の出入りがあるため、消防法上の『防火対象物』に該当します。
そこで、飲食店舗として新たに建物を使用する場合は、使用を始める7日前までに、所轄の消防署に「使用開始の届出」をする必要があります。
(「防火対象物使用開始届」)
内装工事の内容についても届出が必要ですので、工事をご依頼される設計事務所様等にご相談ください。

防火管理者の設置が必要な場合も
飲食店が入っている建物「全体」の収容人数が30人を超える場合、各テナントも、「防火管理者」の設置と「消防計画」の作成・届出が必要になります。
<防火管理者>
防火管理者は、テナントの防火・消防活動の責任者のことで、主な役割としては、①消防計画を作成して届出すること、②定期的な点検・訓練を実施することです。
食品衛生責任者と同様、通常は、オーナーまたは店舗の管理者(店長など)ということになるかと思います。
防火管理者となる人は、建物の規模と、テナントの収容人数により、「甲種または乙種」の「防火管理者講習」を受講する必要があります。
「乙種」は比較的小規模なビル等が対象で、1日の講習で済みます。
「甲種」はそれ以上の規模のビル等が対象で、2日間の研修が必要です。
なお、甲種を受講しておけば乙種のテナントの管理者も兼ねられるほか、日本全国どこへ行っても防火・防災管理者となることが出来ますので、この機に「甲種」の研修を受講しておくのもよいかもしれません。飲食店雑居ビルの実際の火災事例や万が一の場合の対処方法など、とても勉強になります。
費用は、テキスト代のみで5000円ほどです。

<消防計画>
講習を受講して「防火管理者」が決まったら、管理者は「消防計画」を作成します。
消防計画は、お店の規模に応じて「小規模用・中規模用・大規模用」のひな型が消防庁のHPに用意されていますので、これをベースにして、自店に合わせて作成します。
ちなみに、防火管理者の設置と消防計画の作成・届出はお店のオープン後でも大丈夫です。
講習の受講が済み次第、消防計画を作成して、「消防計画作成届」と「防火管理者選任届」を一緒に届け出ます。
まとめ
飲食店を開業するのに直接必要な手続きとしては、
●飲食店営業許可
●社交飲食店の場合は、風俗営業許可
を取得する、ということになりますが、必要に応じて警察・消防への各種届出をも忘れずに行いましょう。
深夜営業の届出をせずに営業をしていると無届営業として処罰の対象になりますし、消防の防火管理者等の届出をせずに万が一のことになれば、経営者の過失責任は免れません(なすべき責務を果たしていないということになります)。
営業がスタートしてからでは忙しくてそれどころではなくなってしまいますので、最初に手続きを済ませておきましょう。
なお、法人経営をお考えの場合は、必ず会社を設立したうえで、会社名義で手続きをされるようにしてください。
営業許可の名義変更という手続きは存在しません。社長個人名義で取得した営業許可を法人名義に移行するには、会社名義で、再度一から許可取得の手続きをすることになってしまいますのでご注意ください。
一日でも早く開業するには?
お電話(平日10:00~19:00)
☎ 050-8888-5179
・「ホームページを見た」とお伝え頂けますとスムーズです
・必ず代表の舘山(たてやま)が対応致します
・お客様対応中などでお電話に出られなかった場合は必ず折り返しご連絡をさせて頂きます
メール(24時間受付)
・お見積りフォームよりご連絡下さい
・土日祝日を除き原則24時間以内にお返事いたします
公式LINE(24時間受付)
・下記のボタンをクリックして友だち追加後、
「お問い合わせ」
「見積り希望」
など、一言メッセージをお願い致します。
※システム上、お客様よりメッセージを頂くまでお返事ができません
※PCでご覧の方は、QRコードが表示されますのでスマホで読み込んでください。
↓↓↓友だち追加はこちら↓↓↓